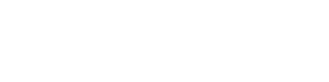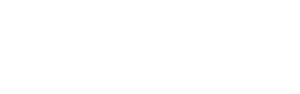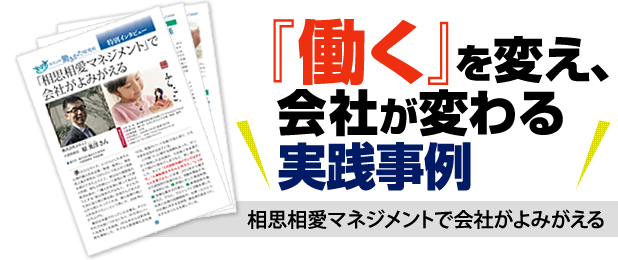取材・文/働きかた研究所 平田未緒
※出典:働くママ&パパに役立つノウハウ情報サイト「日経DUAL」(2015年2月 平田未緒執筆記事を、同サイトのご厚意のもと、転載しています)
浜松に「CS(顧客満足)経営」で、有名な会社がある。
1960年に創業し、今年創立55年を迎える新聞販売店、株式会社柳原新聞店だ。

柳原新聞店外観
同社の特色は、新聞配達をする社員が
自身の配達地域や購読客のことを極めてよく知っていて、その間柄が近いこと。
例えば「お客様ではない、地域の方から『迷い犬を預かっているんだけど、飼い主を知らない?』と相談された」
「秋は配達中にあちこちで柿をもらうので、食べるのが大変」
「夕刊配達時は、お話好きのご高齢者の話をできるだけ聞いているが、
配達が遅れてもいけないので『今日はここまで。明日続きね』と伝えて帰るようにしている」
などといったことが、日常的にある。
こうした結果、新聞全体の購読者数が減少の一途をたどる、極めて厳しい経営環境にありながら、
同社は2014年もまた、個人客からの売上を伸ばした。
売上アップの主要因は、地域の惣菜会社と手を組んだ惣菜・弁当の宅配や、
森永乳業の宅配サービスの伸長だ。
社員が常に顧客のことを考え、顧客との関係が深いから、
同業他社が苦戦する「新規事業」も、同社では軌道に乗るのである。
そう聞くと、「バリバリの正社員として働いてきた」ようだが、そうではない。
入社は33歳のとき、パートタイマーとして、だった。
しかも、いわゆる本業の「新聞販売」とは異なる、小さな部門での採用である。
「下の子どもが幼稚園に入ったのをきっかけに、『パートに行こうかな』とふと思いました。
それで、まずは『県民だより』で見つけた、
県の職員の方と月に一度取材に行って記事を書く“ママさんレポーター”の仕事を始めたのです」

柳原新聞店の取締役、新村久予さん。
きっかけは33歳の時にパートとして働き始めたことだった
「月イチ」の緩いペースで、2年間の任期を終えて、新村さんは次の仕事を探し始めた。
そんな折、求人広告で目に入ったのが、柳原新聞店の「カスタマーレディ募集」の文字である。
「何だろう」。早速電話してみると、説明会を兼ねた面接会に呼ばれ、参加した。
「話を聞くと、カスタマーレディの仕事は、各家庭を飛び込み訪問して
『新聞を購読しているか、していないか。また、新聞への不満は何かを聞き出す』ことでした。
15人くらい応募者が集まっていて皆さん意欲的でしたが、
私は個別面接に呼ばれると『飛び込み訪問なんて、とてもできません』とその場で伝えてしまいました」
新村さんのそうした言葉に、「じゃあ、どんな仕事だったらやりたいですか?」と聞き返した面接官が、
当時の専務で今は社長の柳原一貴さんだった。その柳原さんの質問に、新村さんはこう答えたという。
「最近御社が発行されたミニコミ紙の記事を書く仕事だったらやりたいです」
数日後、新村さんに電話が入る。「ミニコミ紙の記事を書く仕事で、働きませんか」。
これが、20年後には経営の一翼を担うこととなる、柳原新聞店との出会いだった。
「仕事は、毎日1本記事を書くことでした。同じ部署にはパートが4~5人いましたが、
しばらく働いているうちに、社内ではミニコミ紙が『専務の道楽仕事』と呼ばれており、
その制作をする私たちパートは、実は疎外されていることを知りました」
ミニコミ紙は、同社の根幹をなす考え、すなわち
「柳原新聞店の仕事は、単に新聞を売ることではない。
地域の方に情報をお届けし、地域を豊かにすることである」にのっとったもの。
地域とのつながりを深め、CS経営に活かすという、明確な目的を持つ。
にもかかわらず、無料のフリーペーパーであり、直接的な収益を生まなかったことから、
編集部は異端児扱いされていた。
新村さんは振り返る
「これに気づき、ただでさえ引け目を感じていたところ、
当時専務の柳原社長が、なんと『カラー化したい』と言い出して。
もちろん大幅なコスト増です。そこでつい
『広告を入れましょう。私が取ってきます』と言ってしまったんです」
この申し出に、柳原さんは応じた。「取れるなら、取ってきなさい」。
そもそも「飛び込み訪問をするカスタマーレディがイヤで、ミニコミ紙の仕事で入社した」新村さんである。
でも、頑張った。そして、契約を取ってきた。
飛び込み営業、しかも過去に広告掲載の実績が全くない媒体で、である。
「広告営業は、ものすごく大変でした。でも、せっせと営業に走って、飲食店や小売店さんから、
毎月なんとか8件程度は、いただけるようになりました」
その様子を見ていた柳原さんから、驚く指示が降ってきた。
なんと「新聞購読の新規開拓営業もやってほしい」と言われたのだ。
それも、「1年間で50軒の新規購読契約」という、後から聞けば、
同社のマネジャーレベルの、数値目標付きである。

柳原新聞店の社長、柳原一貴さん。
同社の専務だったときに新村さんを採用し、後に取締役に抜擢した
「え、私、パートなのに? と思いましたが、社長の説明はこうでした。
『配達員が日々苦労している新聞営業をやり、
その数字が上がれば、絶対に社内に信頼してもらえる』」
そもそも、「自分たちの頑張りが社内に認められない状況をなんとかしたい」
という気持ち一つで始めた、ミニコミ紙の広告営業。
新村さんは、「社長がそう言うなら」と、ミニコミ紙の原稿書きや、
その広告営業もしながら、新聞の契約獲得に走り始めた。
「毎月平均5件の新規購読契約を自らに課して、頑張りました。
そして、年末には見事50件の、目標達成ができたのです。
振り返れば、このときの経験はその後に大いに活きました。
だから社長には、すごく良い指示をもらったと感謝しています。
ただ、達成感はあったものの、当時の私には、
そもそもの目的である『ミニコミ紙に社員の理解を得る』ことにつながったとは、
感じられませんでした」
そんな彼女に、ある日柳原さんから声がかかる。
「正社員にならないか」
「ちょうどパートで働いて10年目くらいだったと思います。びっくりしました」
新村さんのご主人は、いわゆる“士業”で開業している個人事業主だ。
代わりがきかず、実務負担も重い仕事。
新村さんの相談に対し「正社員にはならないでほしい」とはっきり言った。
「『自分がどんなに大変かわかってほしい』『家を最優先してほしい』という言葉に、
私は共感しました。押し切る気持ちはまったくなく、正社員の話はお断りしたんです」
半面、新村さんにとってミニコミ紙の仕事は、だんだん面白味に欠けてきた。
「飽きっぽくて、おんなじことをずーっと続けていくのが苦痛なんです。
といって正社員になるつもりもありません。これは転職しかないと思って、
柳原社長に退職を申し出ました」
驚いたのは、柳原さんである。しかも、理由を聞くと「繰り返しの仕事をしていたくない」。
その新村さんの言葉に対し、柳原さんはこう言った。
「何を言ってるんだ、俺にはやりたいことが、まだまだいっぱいある。
あなたが飽きないように仕事を与えていくから、続けてほしい」
パートという雇用形態は同じでも、新村さんの仕事人生の、
ここが一つの転換点だったと言えるだろう。
その後新村さんは、まずはカルチャーサロン「エムズ倶楽部」の立ち上げを任された。

現在のエムズ倶楽部(外観)
「エムズ倶楽部は、1回1000円の低料金で、自分の都合に合わせて気軽に参加できる、
地域密着型のカルチャーサロンです。
『柳原新聞店の仕事は、単に新聞を売ることではない。地域の方に情報をお届けし、地域を豊かにすることである』
という当社の考えにのっとり、新聞ご講読者以外の地域の方々にも楽しんでいただける、
文化的サービスを提供しよう、と始めました。
今では、市内2カ所で、年間約90講座を開催するほどに育っています。
でも、最初にこの構想を社長に聞かされたときは、
いったい何をどうしていいのか、全く分からない状況でした。
なので、こうした取り組みで先行していた京急百貨店さんに、教えを請いに行くことから始めたのです」
講師の選定・依頼、告知・集客、会場の確保と当日のセッティング、
また受付から運営など、何から何まで、はじめての経験である。
「飽きて」なんかいられない。というより、無我夢中、必死だった。
「それでも2002年9月、『エムズ倶楽部』は、9講座で無事スタートしました。
カルチャーセンターではなく、カルチャーサロンとしているのは、
地域の方が集う、サロンのような場のほうが、より豊かな交流が生まれると考えたからです。
学べるだけでなく、友達作りもできるようなイメージです。
以来、まる12年が経ち、このコンセプトがまさに現実となってきました。
地域には、例えばフラワーアレンジメントとか、着付けとか、
何かに長けた方がたくさんいらっしゃいます。
そうした方に講師をお引き受けいただき、講師の方も含めた地域の皆が、
金銭的な負担も最小限に、共に学び合う。
そんな、まさにカルチャーサロンが作れていると思います」

エムズ倶楽部看板
そうこうするうちに子どもの手も離れ、新村さんは正社員になった。
「ここからが大変でした。『エムズ倶楽部』が一部の社員が関わる仕事だったのに対し、
その後、任された『ファーブル倶楽部』は、全社全員を動かす仕事だったからです。
これまでとは勝手が違うことを早々に感じ、
『まずは、私という人間を、理解し信頼してもらわないとダメだ』と思いました」
「ファーブル倶楽部」とは、こだわりの栽培をする近隣農家の野菜を、
個人客からの注文に応じて、宅配する事業である。
配達機能はもともと、持っている。そこに新聞だけでなく、地場産の野菜を乗せることで、
地域を支える農家の収入に貢献し、かつ新鮮野菜が欲しい個人客に喜んでもらえると考えた。
しかし、それには自社の社員に、通常の新聞配達以外の配達をしてもらうことになる。
新聞配達員の朝は早い。始業は午前2時半である。
その後、新聞にチラシを折り込み、数社の新聞を配達順に重ねるなどの準備を終えて、
配達に出るのが3時ごろ。配り終えた5時30分ごろにいったん帰宅し、
かつては時期により午後ゆっくり集金などをして、夕方は15時にまた配達に出ればよかった。
野菜の宅配を本格的に始めれば、従来の休みを潰さざるを得ない。
つまり、配達をする社員にとって、労働強化の側面を持っていた。
「ここは、社長からもしっかり説明がありました。新聞だけを扱って、売上を伸ばせる時代ではない。
宅配事業は、配達員も全員、正社員としてしっかり雇用し、給与を支払っていくための手段なのだ、と」
そうやって合意を得て、実際に始めてみると、
はじめて行う「新聞以外」の宅配には想像以上の苦労があった。
段ボールに詰めた野菜は安定性に欠ける。トマトや卵を潰すことなくバイクに乗せて運ぶため、
社員は空き時間を利用して、運転技術を磨くことからスタートさせた。
一方、注文は、一家庭で月に2回程度がせいいっぱい。
事業として成り立つほどのボリュームが出なかった。
そんなある日、当時既に部長に昇格していた新村さんは、
突然社長室に呼ばれる。取締役への就任を打診されたのだ。
「びっくりしました。でも、その場でお断りしたんです。
社長は、『いい加減にしろ』状態でしたが、私にはそう答える理由がありました」
その理由とは、
「社員として雇用される今の部長という役職ならば、定年まで働かせていただける。
でも、取締役になったら定年はなく、事業に失敗した時点で責任を取り、辞めざるを得なくなる。
私はこの会社でずっと働き続けたい。だから取締役にはなりたくない」。
これに対して、柳原さんはこう答えた。
「あなたが辞めざるを得ないときとは、会社全体が潰れるときだ。
責任を取らせて、途中で辞めさせるようなことは絶対にしないよ」。
「この言葉を聞いた瞬間、涙が溢れ出てきました。
さらに『会社が潰れたときは、ごめんね。そのときは一緒に辞めよう』といったことまで言ってくださったのです。
感動しました。そこまで言ってくれる社長がいるだろうか、と」
と、新村さん。そのとき、改めて強く「会社のために頑張ろう」と感じている自分がいたという。

配達スタッフ
その後、新村さんが取り組んだのが、『知久屋夕食宅配事業』である。
「知久屋は、無添加・無着色でお惣菜を作っている、地元では有名な会社です。
そこで作る夕食のお弁当を、ご注文に応じ宅配しようという事業でした。
ところが、この提案を社内にしたところ、社員の大反対に遭いました。
会議室で、机を両手でバンバン叩かれたり・・
『敵対心持ってるんじゃない?』と思いたくなるほどで、憎まれ役とはこのことです」
野菜の宅配のときには出なかった、新たな反対の理由。それは、
「野菜と違って金額が大きい。
しかも新聞のように毎月決まった支払いでもない。
集金できなかったらどうするのか」
「弁当を何層にも積むと、野菜よりさらにバランスが崩れやすい。
もしバイクがひっくり返ったら、本社が配ってくれるのか」
「おかずが弁当箱の中でぐちゃぐちゃになったらどうするのか」
といったもの。これに対して新村さんは「すべて本社が対応する」と言い切った。
こうして実施が決まった『知久屋夕食宅配事業』。
しかし、始まってから新村さんは、驚きの光景を目にすることになる。
「社員達が、弁当を積んで、道の角を曲がる練習をひたすら繰り返しているのです。
聞けば、『野菜とは勝手が違う。お届けする弁当のおかずが中で崩れてしまっていたら、
フタを開けた瞬間お客様にがっかりされてしまうに違いない。
だから、そうならないスピードと角度を、皆で研究しているのです』とのこと、
思わず目頭が熱くなるような気持ちでした」
柳原新聞店では、毎年読者アンケートを実施し、
また社員自らが気づいたことを書く『情報メモ活動』を行っている。
情報メモに書くのは、顧客の声や、社員の声。例えばこんな具合である。
「ちくやのお弁当を食べてもらっているお客様より
『バランスが取れているお弁当なので今年は夏バテしなかったねえ』と言われました。
満足してもらっているようです(著者注:原文ママ)」
「特におせっかいなことはしていませんが、かなり高齢の人や体の不自由なお客様には、
子どもさんは近くにいるんですか? とか夕刊の時には必ず声を掛けるように心掛けているのが、
おせっかいな事かなと思います(同)」
これを日々社員から回収し、柳原社長、新村取締役がまず読んで、コメントをする。

びっしりと書かれた情報メモのコピーの束。
これを全社で回覧する。
例えば前者のメモには「いいね!」、
後者には「いい事です。続けて下さい」といった具合である。
その後、社員全員がすべての情報メモを回覧し読んでいる。
一方、顧客アンケートは、2013年には2909軒分が回収され、
柳原新聞店に「大変満足」「満足」している人が84.6%という結果。
自由回答欄には、他のアンケートでは見られないほど、
びっしりとコメントが書かれている。
しかもこのコメントを、内容別に分類すると「お褒め」が83.1%、「要望」が10.5%、
「不満」4.5%という状況。
これも、もちろん回覧する。
情報メモ活動をはじめて10年が経ち、今では年間2000枚以上が集まるという。
一方の読者アンケートは、2000年にスタートし、毎年とり続けて既に15年が経過した。
「最初は情報メモも、全く集まりませんでした。もちろんアンケート結果もここまで良くはありません。
ところが、この二つの活動を地道に行った結果、
社員は、お客様のことに本当に詳しくなりました。
逆にお客様にも社員のことを、本当によく覚えていただいています」

今では年間2000枚以上集まる読者アンケート
自由回答欄のフリーコメントはどれもびっしり
こうしたつながりがあるから、『森永ミルク事業』や『知久屋夕食宅配事業』が軌道に乗る。
一方で、つながりがあるからこそ、社員は宅配事業に慎重だった。
「お客様をがっかりさせるような、無責任な配達はできない」という思いが、常に社員をそうさせたのだ。
住み込みで働けることも多い新聞販売店は、
かつては「流れ者の巣窟」と言われたりしたこともあると聞く。
「人が入っては辞め、新規購読の勧誘は、中にはやくざまがいな例もあった」という。
柳原新聞店とて、状況は大差なかった。
ところが、今や社内にかつての面影は全くない。
新村さんの口から、頻繁に出る言葉がある。
「うちの社員は、本当にすごいと思うんです」
「自画自賛で申し訳ないのですが、うちの社員は素晴らしいんです」
パートで入社し、様々な壁を乗り越えてきた。
そんな体験を持つ新村さんの「現場を思う気持ち」「社員を称賛する気持ち」が、
社長の思いと共に、社員にまっすぐに伝わっている。
だからこそ、社員が自分の仕事に誇りを持ち、お客様のほうを向けるのだ。
[終わり]
顧客アンケートで「心を通い合わせる」経営手法【長野第一ホテル】第4回
2017 07 05
<< 目次 >> 第1回 老朽・閑古鳥ホテルを黒字化、賃金アップできた理...
顧客アンケートで「心を通い合わせる」経営手法【長野第一ホテル】第3回
2017 07 05
<< 目次 >> 第1回 老朽・閑古鳥ホテルを黒字化、賃...
顧客アンケートで「心を通い合わせる」経営手法【長野第一ホテル】第2回
2017 07 04
<< 目次 >> 第1回 老朽・閑古鳥ホテルを黒字化、賃...